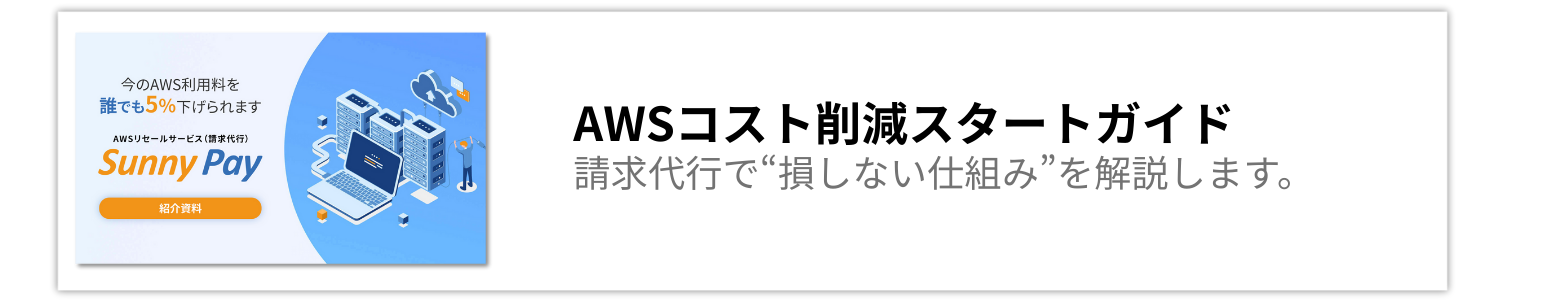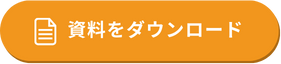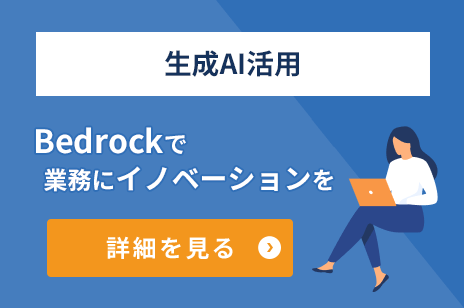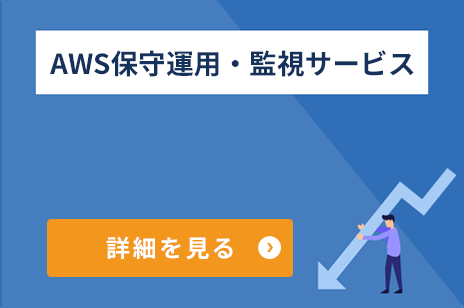AWSを使い始めた企業がEC2インスタンスを立ち上げると、ほぼ自動的にセットで使うことになるのがEBS(Elastic Block Store)です。
しかし、このEBSについて「とりあえずデフォルトで使っている」「コストがかかっているのは知っているけど仕組みはよく分からない」といった声も少なくありません。
EBSはAWSにおける“ストレージの要”とも言える存在であり、EC2の利用だけでなく、データの永続化、バックアップ、復旧、さらにはパフォーマンス設計にも密接に関わってきます。
本記事では、EBSの仕組みからタイプごとの違い、気づきにくいコスト構造、最適化のヒントまでを網羅的に解説します。EBSを正しく理解すれば、今よりももっと安心・効率的にAWSを使いこなすことができるはずです。
この記事はこんな人にオススメ!
- EC2を使っているが、EBSの仕組みや料金構造がよく分からない
- スナップショットの管理や削除をどうすべきか迷っている
- AWS全体のコストを見直すきっかけを探している
1.EBSとは何か?S3との違いと役割
EBSは、AWSにおいてEC2インスタンスの“ハードディスク”のような役割を担うブロックストレージサービスです。EC2に対して一つまたは複数のEBSボリュームを接続し、OSやアプリケーションのファイルを格納・読み書きできるようにします。
この点で、S3のようなオブジェクトストレージとは性質が異なります。S3が「画像やドキュメントなどのファイルを保管する倉庫」だとすれば、EBSは「サーバーが直接読み書きするためのハードディスク」というイメージが近いでしょう。
もうひとつの大きな特徴は、EBSのデータは同じアベイラビリティゾーン(AZ)内において、複数の物理インフラにまたがって自動的に冗長化されているという点です。これにより、高い可用性と耐障害性を保ちながら、EC2を停止・削除してもデータを永続化できるというメリットがあります。

2.ストレージタイプの違い
EBSには複数のストレージタイプが存在し、用途やパフォーマンス要件によって選択する必要があります。最もよく使われているのは、汎用SSDである「gp3」タイプです。バランスの取れた性能とコスト感が特徴で、読み書きが標準的なアプリケーションに適しています。
一方で、非常に高いIOPS(I/Oの回数)を必要とするデータベース用途などには「io2」や「io2 Block Express」などの高性能SSDタイプが用いられます。これらはパフォーマンス保証付きですが、コストも相応に高くなるため、選定には注意が必要です。
さらに、コールドデータや大量のスループットを求めるバッチ処理用途では、「st1」や「sc1」といったHDDベースのストレージも存在します。ただしこれらはランダムアクセスに弱く、利用できるインスタンスタイプにも制限があるため、限定的なシーンでの採用が一般的です。

スループット/ボリューム…単位時間あたりに転送できるデータ量を示す性能
3.意外と知らないEBS料金のしくみ
EBSの料金は非常にシンプルに見えて、実際にはいくつかの見落とされがちなポイントがあります。まず大前提として、EBSはボリュームのプロビジョニング(割り当て)容量に対して、月額で課金されます。つまり、EC2が起動しているかどうかに関わらず、EBSに割り当てた容量ぶんの料金は常に発生し続けます。
さらに、io2など一部のストレージタイプでは、IOPSの上限設定に対しても料金が発生します。また、リクエスト数やスループットが多い場合にも追加料金が加算されるケースがあります。これらは「使った分だけ」の従量課金ではなく、あくまで“設定した上限”や“プロビジョニングした性能”に対する課金であるため、使いきれていない状態でもコストが発生するのが厄介な点です。
また、EBSのバックアップとして利用されるスナップショットも、実は料金発生ポイントの一つです。S3に保存される仕組みで、差分データのみ課金されるものの、頻繁にスナップショットを作成していたり、古いものを残しっぱなしにしていると、気づかないうちに数十〜数百GB単位のコストが加算されていることもあります。
| ボリュームタイプ | 料金(2025年9月時点) |
| 汎用 SSD (gp3) – ストレージ | USD 0.08/GB 月 |
| 汎用 SSD (gp3) – IOPS | 無料の 3,000 IOPS、および 3,000 を超えた分について 1 か月におけるプロビジョンド IOPS あたり USD 0.005 |
| 汎用 SSD (gp3) – スループット | 無料の 125 MB/秒、および 125 を超えた分について 1 か月におけるプロビジョンド MB/秒あたり USD 0.040 |
| 汎用 SSD (gp2) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり USD 0.10 |
| プロビジョンド IOPS SSD (io2) – ストレージ | USD 0.125/GB 月 |
| プロビジョンド IOPS SSD (io2) – IOPS | 1 か月におけるプロビジョンド IOPS (最大 32,000 IOPS まで) あたり USD 0.065 |
| 1 か月におけるプロビジョンド IOPS (32,001~64,000 IOPS) あたり USD 0.046 | |
| 1 か月におけるプロビジョンド IOPS (64,000 IOPS 超) あたり USD 0.032 | |
| プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり USD 0.125、さらに 1 か月にプロビジョニングされた IOPS あたり USD 0.065 |
| スループット最適化 HDD (st1) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり USD 0.045 |
| Cold HDD (sc1) ボリューム | 1 か月にプロビジョニングされたストレージ 1 GB あたり USD 0.015 |
4.放置がコストを生む、EBSの“あるある”
多くの企業が陥る落とし穴のひとつに、「EC2を停止・削除したあとも、EBSがそのまま残っている」というケースがあります。
実際には、インスタンスだけを止めても、接続されていたEBSボリュームは保持されており、その分のストレージ料金は引き続き請求されます。検証環境や一時的なプロジェクトでこれを繰り返していると、使っていないはずのEBSに対して料金が発生し続けるという、もったいない状況に陥りがちです。
また、前述の通り、用途に合っていないストレージタイプを選んでしまうことも、無駄なコストの原因になります。たとえば、IOPSがそれほど求められないにもかかわらずio2を選んでしまうと、必要以上の性能と料金を払っている状態になります。
さらには、スナップショットの“溜めっぱなし”も注意が必要です。週1回の自動スナップショットを半年以上放置したまま…といったケースでは、思わぬタイミングでEBS関連コストが跳ね上がることもあり得ます。
5.ストレージの最適化、どう進める?
EBSコストを最適化する第一歩は、自社で利用しているボリュームの構成を“棚卸し”することから始まります。特に複数のプロジェクトが並行して走っている企業の場合、いつのまにか未使用のEBSが残っていたり、用途の異なるボリュームが混在していたりすることは珍しくありません。
ここで重要になるのが「環境ごとの切り分け」と「ストレージタイプの適正化」です。プロダクション環境にはio2やgp3など性能重視のタイプを、本番以外のテスト環境や開発用途にはコスト効率の良いgp3やst1を割り当てることで、無理のない最適化が可能になります。
また、定期的にTrusted Advisorなどのツールを使って「使用率が低いボリューム」「接続されていないEBS」「長期間変更がないスナップショット」などを洗い出し、不要なものを削除・統合していく運用体制を整えることも重要です。
▼以下の記事で、EBSにまつわるコスト削減方法について分かりやすく解説しています▼
【古いEBSやスナップショット、たまりすぎてませんか?今すぐできるストレージコスト見直し術】
6.SunnyPayを活用した“もう一段階”上の最適化
EBSのコストは「使いすぎない」ことだけが正解ではありません。むしろ、“必要な分はしっかり使いつつ、賢く支払う”という視点が求められます。
たとえば、SunnyPayではEBSの利用料金も請求代行の対象となっており、利用分に対して最大5%の割引が適用される仕組みになっています。この割引は、ストレージの種類や容量に関係なく適用されるため、ボリューム単位での細かな調整をしなくても一定の削減効果が得られます。
さらに、SunnyPayでは請求状況やサービスごとの利用量をグラフ形式で月次レポートとして確認できるため、「EBSが高いと思っていたけど、実はスナップショットの積み上げだった」といった可視化も可能になります。
構成を変えず、ルートアカウント権限の譲渡も不要なまま導入できる点も、クラウド管理の手間を増やさない大きな利点です。
▼AWS請求代行サービス「SunnyPay」のサービス資料はこちら▼
【資料をダウンロードする】
まとめ:EBSを知れば、AWSがもっと効率よくなる
いかがでしたか?
EBSは、EC2の裏側で地味にコストを生んでいる“見えにくい存在”です。しかしだからこそ、正しく理解し、使い方や選び方を見直すだけで、大きな最適化のインパクトを生み出せるパーツでもあります。
AWSの中核サービスであるEBSをきちんと理解することは、クラウドコスト全体を見渡す力にもつながります。
今の自社の使い方に合った構成になっているか、定期的にメンテナンスされているか、スナップショットの管理は適切か──。
小さな見直しの積み重ねこそが、無理なく続けられる最適化の第一歩です。
そして、SunnyPayのようなツールをうまく組み合わせることで、運用負荷を減らしながら“使う分だけきちんと最適化されたAWS”へと近づくことができます。
EBSを含めたAWSの利用料金、もう少し最適化できるかもしれません。
SunnyPayなら、EBSやEC2など主要サービスの利用料に最大5%の割引が適用され、支払いを“無理なく”見直すことが可能です。
Root譲渡不要、既存構成もそのまま。まずは資料で仕組みをご確認ください。