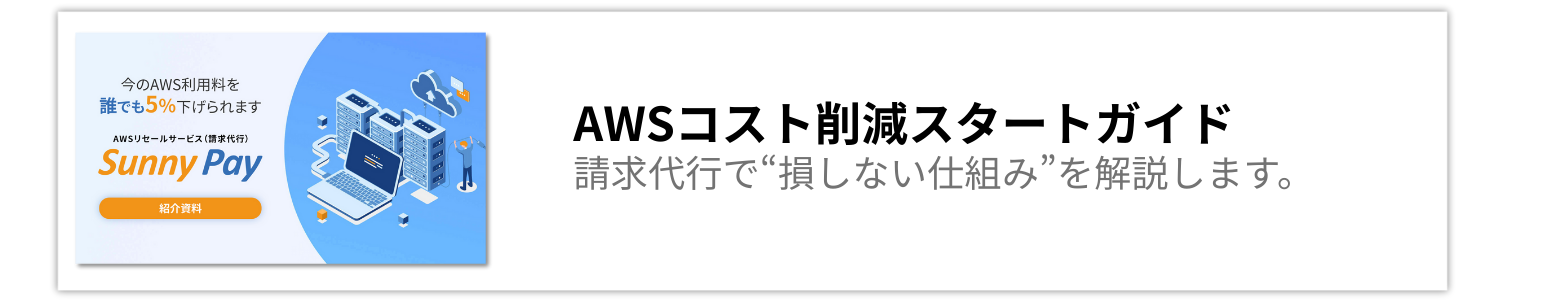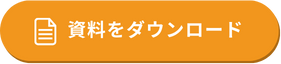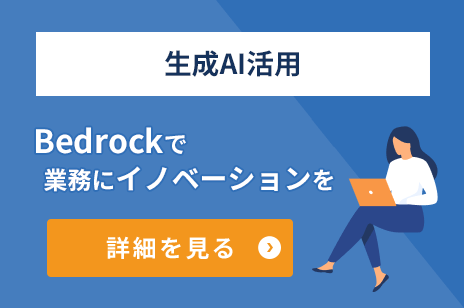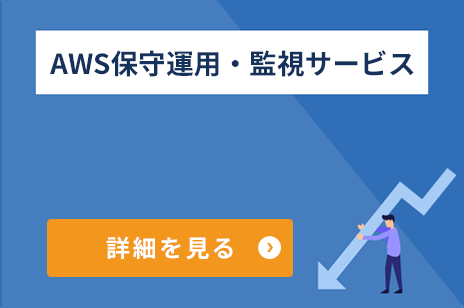AWSのリザーブドインスタンス(RI)は、クラウドコストの最適化を考える上で王道とも言える手段です。最大72%の割引率という数字は強力で、「とりあえずRIを導入しておこう」と考える企業も少なくありません。
しかし、実際に導入した後にこうした声を聞くことがあります。
「RIを買ったのに、請求額がオンデマンド時代とあまり変わらない」
「誰のアカウントに割引が効いてるのか、まったく見えない」
「開発チームと経理の間で認識がズレてしまう」
それもそのはず。RIの割引は、購入して終わりではなく、正しく設計・運用・共有されて初めて“効果”になるからです。
本記事では、リザーブドインスタンスの割引が「効いていない」ように見える背景と、それを回避するための構成設計・可視化・請求連携のポイントについて解説します。
この記事はこんな人にオススメ!
- リザーブドインスタンスを契約したのに、割引の実感がない
- RIの購入と適用に関する設計や共有設定に不安がある
- 経理部門との間で「RIのコスト効果が見えない」と悩んでいる
▼前編では「RIを導入したけどうまく使いこなせない」というよくある失敗パターンを解説しています▼
リザーブドインスタンスの落とし穴とは?AWS請求と構成で損しないために
1.RI割引が「効かない」構成とは?
リザーブドインスタンスの適用は、AWSアカウント構成と密接に関係しています。
よくある課題は以下のようなパターンです。
まず、複数アカウントを運用している企業で、「RIを買ったアカウント」と「実際にインスタンスを稼働させているアカウント」が異なる場合、RIの割引が正しく適用されないケースがあります。
このようなズレを防ぐには、AWS Organizationsを利用した一括請求(consolidated billing)と、RI共有の有効化が必須です。RIの割引は、同じ組織内であれば共有することが可能ですが、それを有効にしないまま運用を続けていると、購入したRIが本来の効果を発揮できません。
また、RIは“指定したインスタンスタイプ”に対してしか適用されません。組織的にインスタンスタイプの変更が頻繁に行われる環境では、RIの適用率が低くなりがちです。「EC2は統一して使う」「RI適用対象はしばらく固定する」といった構成の方針設計も、割引効果に大きく影響します。
2. 経理と技術の間にある“見えない壁”
RIの効果が社内でうまく共有されない原因の一つが、経理部門と技術部門で「見るレポートが違う」ことです。
技術担当者はAWSマネジメントコンソールやCost Explorerを見て、「RI割引が適用されている」ことを確認できます。ところが経理が扱う請求データは、月次のPDF請求書やCSV出力の明細などで、RI割引がどこにどう効いているかが非常に分かりづらいのです。
さらにやっかいなのが、RIの割引適用はインスタンスごとに細かく自動で割り振られるため、「何がどれだけ安くなったのか」を人間の目で把握するのが難しい点です。
このズレにより、社内では次のようなギャップが生まれます:
技術:「ちゃんと割引効いてますよ」
経理:「でも請求額に変化がないように見える」
管理職:「なんか、うまくいってない気がする」
RIのコスト効果を“伝わる形で”共有するには、組織内で使うレポートのフォーマットや共有ルールを整備する必要があります。割引が見えていないのではなく、「見える化されていない」だけのことも多いのです。
3.請求代行を導入すると、割引が消えることもある?
AWSの請求代行サービスを使うと、「RIの割引がうまく反映されなくなる」リスクも存在します。
これは、すべての請求代行サービスがAWSの仕組みに完全準拠しているとは限らないからです。中には、自社の請求処理ロジックを適用していたり、割引表示を調整していたりする事業者もあります。
その結果として起こるのが、以下のような課題です:
- RIの割引が請求書上では見えなくなる
- 実際にRIが適用されているか不明確になる
- 割引の適用タイミングがAWSの動きとズレる
表面上は「請求書がまとまって見やすくなった」ように見えても、その裏でRIの恩恵が薄れている、というケースも珍しくありません。
だからこそ、請求代行を選ぶ際は、「支払い方法」だけでなく、「AWSの割引構造が壊れないか」という視点での選定が重要です。
4.SunnyPayなら、RIにも“ダブルで”割引が効く
SunnyPayは、AWS本来のRI構成・割引ロジックに一切手を加えることなく、企業側の支払い面だけを柔軟に最適化する仕組みです。
特に大きなメリットは次の2点です:
1つ目は、リザーブドインスタンス購入時にも5%の割引が適用されるという点。
これは他の請求代行ではあまり見られない特長で、「すでにAWSから割引されているRI」に対して、さらにSunnyPay独自の割引が重なることで、実質的な割引率がさらに上がるという仕組みです。
2つ目は、AWS側の設定や構成に一切の干渉がないという点。
RIの購入はこれまで通りマネジメントコンソール上で行い、割引の適用もAWS本体のロジック通りに進行します。SunnyPayはあくまで「請求の代行」と「支払いの最適化」を担い、技術運用の妨げになることはありません。
このように、RIの割引を損なわず、むしろ最大限に活かせる状態で請求処理ができるのは、SunnyPayの大きな差別化ポイントと言えるでしょう。
まとめ:RIを“効かせる”のは、設計と可視化の力
いかがでしたか?
リザーブドインスタンスは、買うだけでは効果が出ません。
必要なのは、構成設計、アカウント共有、レポートの可視化、経理との連携、そして割引を殺さない請求の仕組みです。
とくにRIのような“裏側で効いている”割引構造は、可視化されてはじめて社内的な信頼を得ます。
SunnyPayなら、そのRIにさらに5%の割引を重ねることで、効果を「数字で見える形」にしながら、AWSの設計や運用フローに干渉することなく導入できます。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
▼前編では「RIを導入したけどうまく使いこなせない」というよくある失敗パターンを解説しています▼
リザーブドインスタンスの落とし穴とは?AWS請求と構成で損しないために
AWSコスト削減セミナー、参加受付中!

「気づかぬムダをどう見つけ、どう減らすか?」
そんな疑問に応える、AWSコスト削減に特化した無料ウェビナーシリーズを開催中です。
次回は、「RI/SPの活用と料金管理の見直し」をテーマに、コスト最適化に直結する4つの代表的な施策を解説します。
“契約”と“構成”の両面からAWSコストを最適化するポイントを30分で凝縮してお届けします。
リザーブドインスタンスを“正しく活かす”ための資料はこちら
RIの共有設定や運用設計、割引適用の可視化方法などを一冊にまとめました。
SunnyPayなら、RI購入にも5%割引が適用されることを含め、請求全体の最適化が可能です。