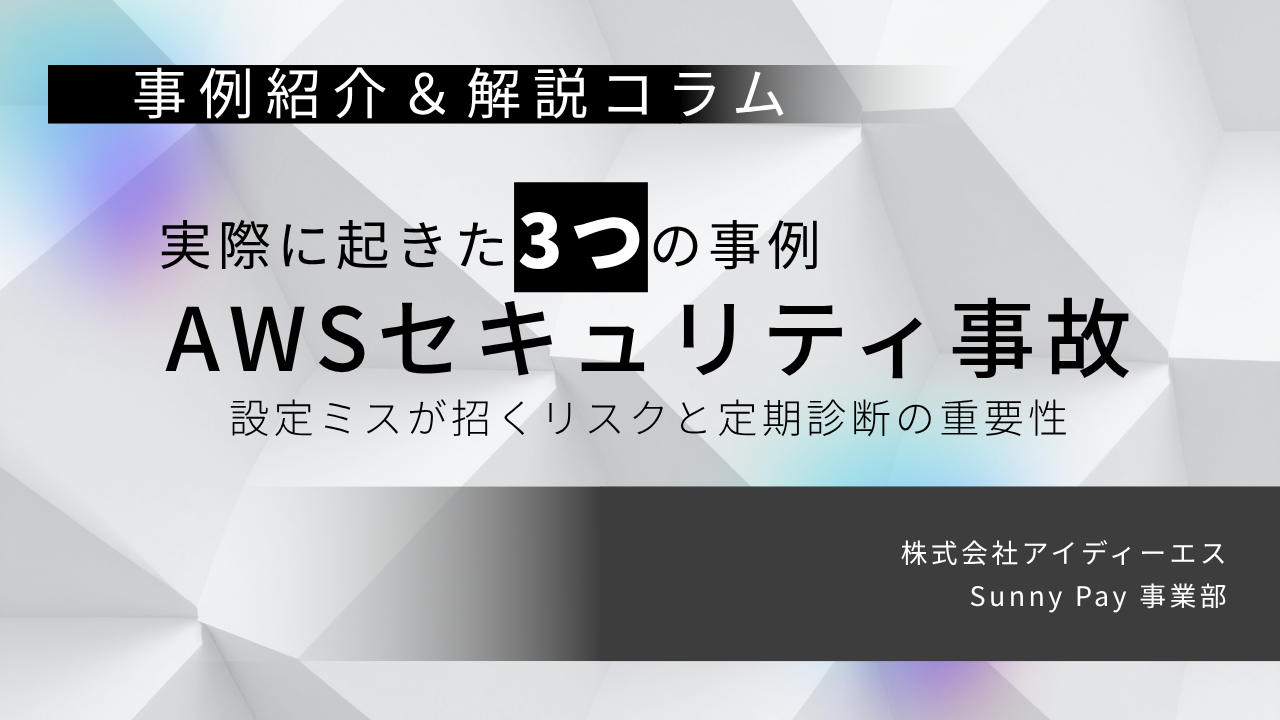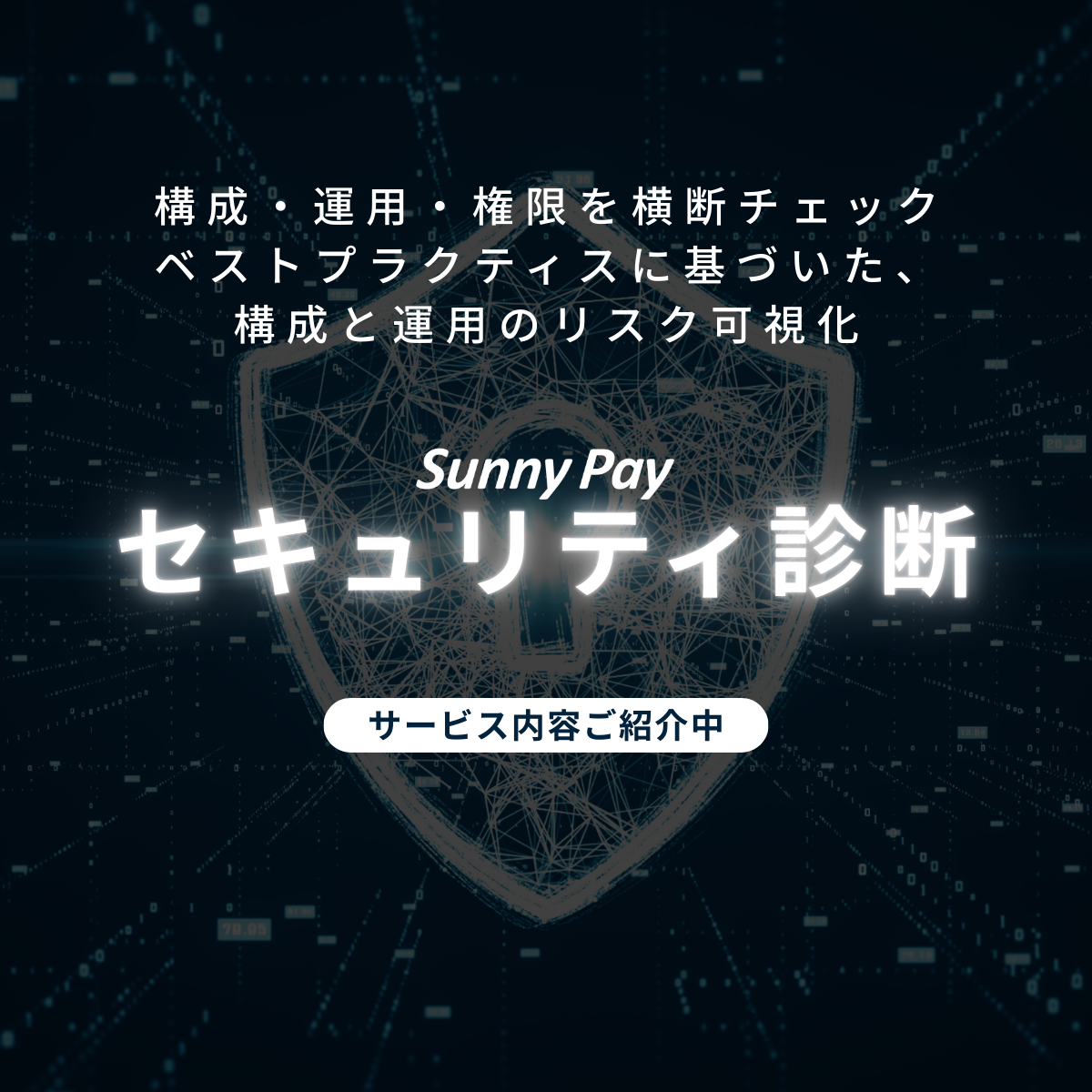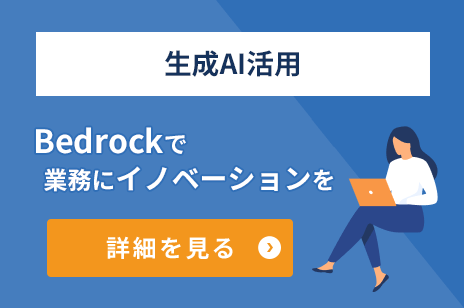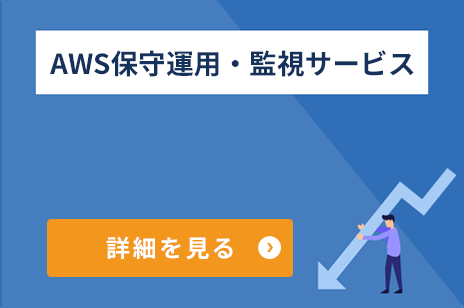この記事はこんな方におすすめです。
- AWSの設定や権限管理に不安があり、「自社の環境が安全か」を一度確認したい方
- クラウド環境でのセキュリティ事故の実例を知り、具体的な対策や診断方法を理解したい方
- AWS Security Hub CSPMを使った構成診断の内容や、どの程度リスクが分かるのか知りたい方
AWSは優れたセキュリティ基盤を持つクラウドサービスであり、多くの企業が業務の中核として活用しています。しかし、その一方で「AWSを使っている=安全」という誤解も広がりやすく、設定ミスや運用の見落としによってインシデントが発生するケースは後を絶ちません。
クラウドのセキュリティは、AWSと利用者がそれぞれの責任範囲を分担する「責任共有モデル」で成り立っています。つまり、AWSがクラウドの“中身”を保護する一方、環境の設定・権限・公開範囲といった“使い方”の部分は利用者側の責任となります。
この理解不足が、思わぬ事故につながることがあります。
ここでは、実際に発生したセキュリティ事故を3つ取り上げ、どのようにしてトラブルが起きたのか、そしてその再発を防ぐために何をすべきかを整理していきます。
■目次
1.《事例1》設定不備を突かれた大規模情報漏えい
2.《事例2》パブリックIPの運用ミスが攻撃の糸口に
3.《事例3》SSHの開放によるブルートフォース侵害
4.なぜ事故が繰り返されるのか
5.セキュリティ診断が果たす役割
まとめ:AWSを安全に使うための“前提条件”としての診断
《事例1》設定不備を突かれた大規模情報漏えい
IMDS経由でIAM権限が盗まれた事例

金融大手のA社では、AWS上で運用していた独自WAF(ModSecurity)の設定不備を突かれ、SSRF(Server-Side Request Forgery)攻撃を受けました。
攻撃者はEC2インスタンス上の IMDS(Instance Metadata Service)v1 にアクセスし、IAMロールの一時的な認証情報を取得。
その認証情報を使ってS3にアクセスし、約1億人分の個人情報が外部に流出する事態となりました。
この事例は「AWSそのものが破られた」のではなく、「設定の誤りを突かれた結果としてAWS上の権限が悪用された」ことが原因です。IMDSはv2でセッションベース認証が強化されていますが、v1のまま構成されていたことが脆弱性を生みました。
ポイントは、AWSが提供する強固な機能も、適切に設定されなければ意味をなさないという点です。
また、AWSでの環境構築がされている場合は、Amazon Guard Duty(脅威検知サービス)の有効化や、IMDSv2への切り替えを検討する必要もありそうです。
《事例2》パブリックIPの運用ミスが攻撃の糸口に
EIPハイジャックの悪用例

報告があった事例では、攻撃者がすでに侵害済みのAWSアカウントからElastic IP(EIP)を“転送(transfer)”し、攻撃者自身のアカウントでそのIPを悪用したとされています。
攻撃者は被害者のIPを利用し、信頼を装ったフィッシングや不正通信に利用できてしまいました。
この問題は「EIPという仕組みそのものが危険」という話ではなく、
- パブリックIPv4の管理が不適切
- 権限設定が緩く、操作が許されていた
といった運用側の問題が主因です。
AWS Security Hubでも「パブリックIPv4は必要最小限に」というベストプラクティスが示されており、外部にIPを晒さない構成が推奨されます。
《事例3》SSHの開放によるブルートフォース侵害
EC2の“基本的な設定ミス”から発生した事故

別の例では、EC2インスタンスにパブリックIPが付与され、SSH(TCP/22)がインターネットへ開放された状態になっていたことで、ブルートフォース(総当たり攻撃)を受けて侵害につながりました。
ブルートフォース攻撃自体は特に高度なサイバー攻撃ではありませんが、脆弱なパスワードに有効であること、また自動化ツールによって実行が容易であることから依然として根強く残っています。
対策としては非常にシンプルで、
- SSHを全開放しない(0.0.0.0/0の禁止)
- 接続元IPを制限する
- SSM Session Managerの利用に切り替える
- 多要素認証(MFA)を導入し、パスワードベースのログインを無効化する
といった基本的な構成を徹底するだけでリスクは大幅に減らせます。
逆に言えば、“基本的なベストプラクティスで防げる事故が依然として多い”ということです。
なぜ事故が繰り返されるのか
共通点は「設定の見落とし」と「構成の複雑化」
これらの3事例はまったく別の攻撃手法で起きていますが、根本原因は共通しています。
- 仕様を理解しないまま利用してしまう
- 設定項目が膨大で、どこかに抜け漏れが発生する
- 権限や公開範囲が広すぎる
- 過去の運用を放置してしまう
AWS環境は柔軟に拡張できる反面、設定項目は数千にも及びます。すべてを手動で確認し続けることは現実的ではありません。
そこで必要となるのが「構成診断」による定期的なチェックです。
セキュリティ診断が果たす役割
AWS Security Hub CSPMを活用した“構成の見える化”
IDSが提供するSunnyPayのセキュリティ診断サービスは、AWS Config と AWS Security Hub CSPM を活用し、AWS環境の設定リスクを自動的に評価します。
IAM権限、S3の公開設定、EC2/VPCのネットワーク構成、ログ管理(CloudTrail・Config)、暗号化やパスワードポリシーなど、多岐にわたる項目をベストプラクティス基準で検査し、「低/中/高/重大」 の重大度に分類してレポート化します。
レポートでは、
- 設定の問題点
- 想定される影響範囲
- 推奨される対策
を脅威度別に示すため、改善計画の立案に直結します。
「どこから直せばいいか分からない」という課題が、“何をどう直せば良いかが分かる状態”に変わるのが最大の価値です。
まとめ:AWSを安全に使うための“前提条件”としての診断
AWSは非常に強固なクラウドサービスですが、
安全性は「AWSが守る領域」と「利用者が守る領域」の双方が機能して初めて成り立ちます。
今回紹介した3つの事例は、いずれも設定の見落としや運用上の油断から発生したものです。
クラウドの利便性を最大限に活かすには、構成の可視化と継続的な見直しが欠かせません。
SunnyPayのセキュリティ診断サービスは、
そうした“予防策”を短期間で実現するための仕組みです。
AWS環境を安全に運用する第一歩として、一度診断を検討してみてはいかがでしょうか。
AWS環境のセキュリティ、確認できていますか?
AWS環境のセキュリティリスクは、攻撃だけでなく、設定や運用の見落としから生まれるケースも少なくありません。
自社環境の状態を整理したい方は、当社が提供しているセキュリティ診断の紹介記事もあわせてご覧ください。
また、診断内容やチェック項目をまとめた詳細資料もご用意しています。