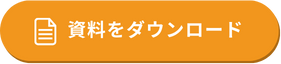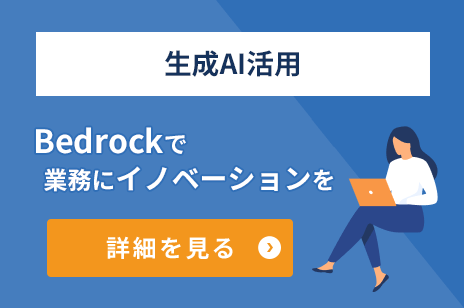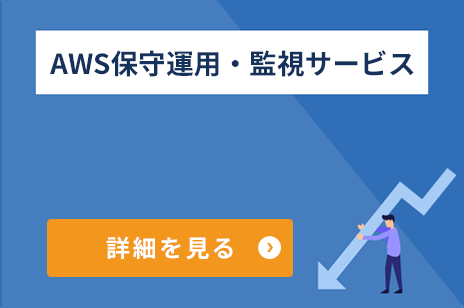AWSを使っていると、「リザーブドインスタンス(RI)を使うとコストが安くなるらしい」という話を耳にする機会があります。オンデマンドインスタンスに比べて最大72%の割引が効くと聞けば、多くの企業が一度は検討する機能でしょう。
しかし現場の実態はやや異なります。「RIを導入したのに、期待していたほどコストが下がらなかった」「実際のところ割引されているかどうか分からない」「買ったはいいけど、使い方がよく分からない」といった声も多く聞かれます。
リザーブドインスタンスは確かに強力な節約手段ではありますが、その効果を最大化するには、正しい理解と運用が不可欠です。本記事では、よくある誤解や失敗パターンを掘り下げ、RIの適切な導入・活用のヒントを解説します。
この記事はこんな人にオススメ!
- リザーブドインスタンスを買ってみたものの、効果を実感できていない
- AWSコストの最適化に取り組んでいるが、うまく成果が出ていない
- 請求代行サービスとの併用で、RIの割引が正しく反映されているか不安
1.そもそもリザーブドインスタンスって何?
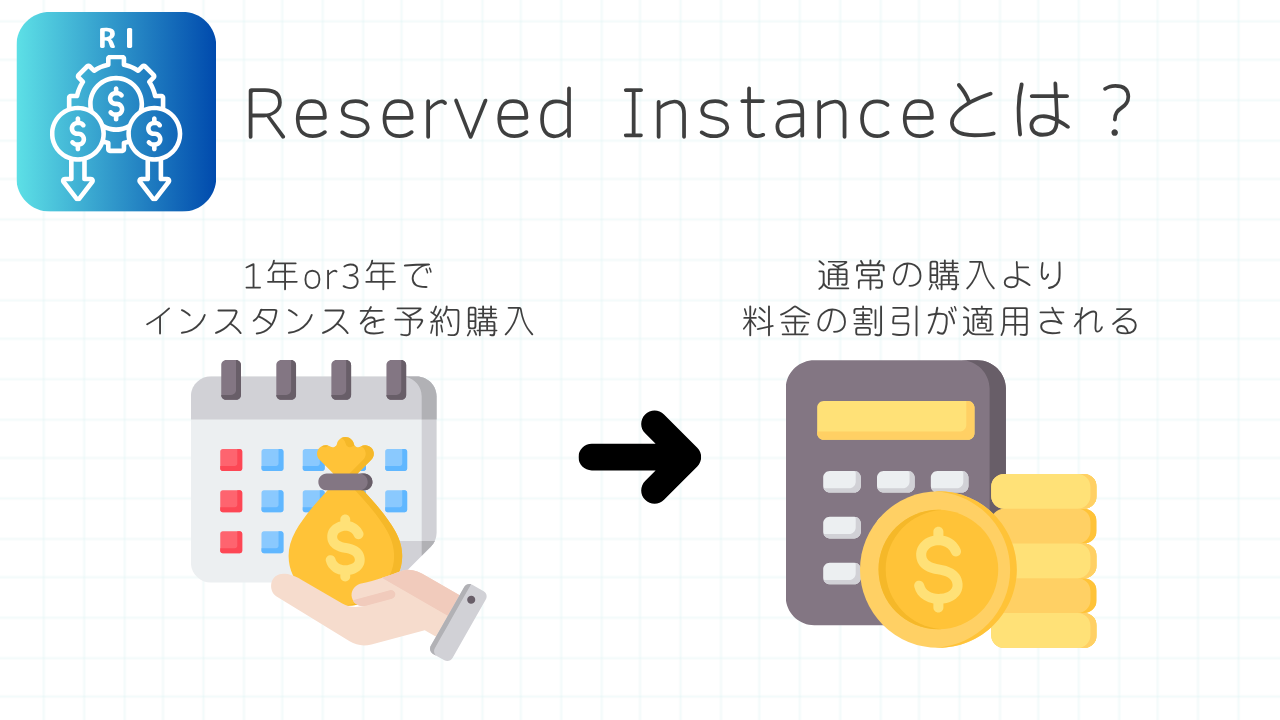
RI(リザーブドインスタンス)とは、特定のインスタンスを「1年または3年間使い続ける」という前提で“予約購入”することで、オンデマンド利用よりも割安にインスタンスを使える制度です。主にEC2(仮想サーバ)やRDS(データベース)などのサービスに適用されます。
RIには2種類あります。一つは「スタンダードRI」で、契約時に指定したインスタンスファミリーやタイプを変更することができない代わりに、割引率が最も高くなります。
もう一つは「コンバーチブルRI」で、こちらはインスタンスタイプなどの変更が可能ですが、割引率はやや低めです。
また、適用の範囲(スコープ)にも違いがあります。アベイラビリティゾーンを指定するゾーンスコープの場合は、対象となるゾーンでのみ適用される代わりに、キャパシティの確保も行われます。一方、リージョンスコープは、より柔軟に適用されますが、リソースの確保は保証されません。
このように、RIは種類・期間・スコープの掛け合わせによって最適な形が異なり、その理解が浅いまま契約すると、思わぬミスマッチが起きる可能性があります。
2.リザーブドインスタンスの“あるある失敗”4選
利用率が低く、むしろ損をしてしまう
RIは「使っても使わなくても料金が発生する」仕組みです。オンデマンドとは異なり、常時稼働させてはじめて割引の恩恵が得られるため、開発環境や夜間停止しているサーバに適用しても意味がありません。利用時間の短い用途にRIを導入すると、むしろコストがかさむ結果になることもあります。
構成変更によって使えなくなる
インスタンスタイプやリージョンを途中で変更すると、適用対象が変わってしまい、RIの割引が適用されなくなるケースがあります。特にスタンダードRIは変更ができないため、構成が固まっていないうちに契約してしまうと、使いきれないまま期間が終了してしまうこともあります。
アカウント構成が分かれていて割引が効いていない
AWS Organizationsを利用して複数アカウントを管理している場合でも、「RI共有の設定」を有効化していないと、割引が親アカウントのみに限定され、実際に利用しているサブアカウントには割引が適用されないといった問題が起こります。
「買って満足」で放置される
せっかく購入したRIの適用状況を、後から確認していないケースも多く見られます。Cost Explorerや利用状況レポートを活用して、RIの消化率を定期的に確認することが重要ですが、それが行われないと「効果があったのかどうか分からない」という事態に陥ります。
3.RIは誰にとって本当に意味があるのか?
リザーブドインスタンスが効果的なのは、「ある程度予測可能で、常に一定量のリソースが必要な環境」においてです。たとえば、Webアプリケーションの本番サーバや、長期運用を前提としたデータベースサーバなどが該当します。
逆に、検証用の短期サーバや利用頻度の低いサービス、構成が頻繁に変わるスタートアップフェーズのプロジェクトなどには、必ずしもRIが適しているとは限りません。オンデマンドやスポットインスタンスの方が、柔軟でかつコスト効率が良いケースもあります。
4.RI導入時に考えるべき3つの視点
導入前に確認しておくべきなのは、次の3点です:
| 項目 | チェックすべきポイント |
| 技術構成 | 今後1〜3年、構成が大きく変わらない見込みがあるか? |
| 利用スタイル | インスタンスを常時稼働させる必要があるか? |
| 組織構成 | Organizations利用時、RI共有設定が有効になっているか? |
この3つが揃って初めて、RIは最大限の効果を発揮します。「なんとなくコスト削減になりそうだから」と曖昧なまま導入するのは避けたいところです。
まとめ:割引率だけじゃない、“使いこなせるか”が鍵
いかがでしたか?
リザーブドインスタンスは、AWSのコスト最適化において有力な選択肢です。ですが、その実力は「契約しただけ」では引き出されません。導入の適正を見極め、構成とアカウントを整え、定期的に利用状況を確認する――この運用があってこそ、割引率の恩恵が本当に意味を持ちます。
「買ったのに割引されていない」「使いこなせていない」といった声が後を絶たないのは、RIという仕組みが持つ前提条件や制約が、正しく理解されずに導入されているからかもしれません。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
AWSコスト削減セミナー、参加受付中!

「気づかぬムダをどう見つけ、どう減らすか?」
そんな疑問に応える、AWSコスト削減に特化した無料ウェビナーシリーズを開催中です。
次回は、「RI/SPの活用と料金管理の見直し」をテーマに、コスト最適化に直結する4つの代表的な施策を解説します。
“契約”と“構成”の両面からAWSコストを最適化するポイントを30分で凝縮してお届けします。
▼割引、ちゃんと効いてますか?|リザーブドインスタンスの”損しない使い方”を資料で解説しています▼
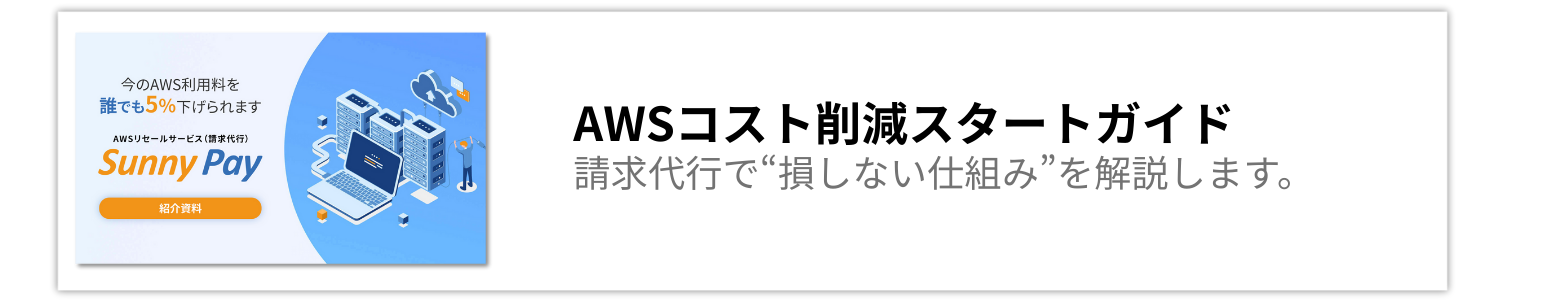
後編:RIをちゃんと効かせるには、請求と構成の見直しが必要です
後編では、RIの効果を最大化するために必要なアカウント設計や、Organizationsによる共有設定、さらには請求代行サービスを使う際に気をつけるべき落とし穴について掘り下げていきます。
特に注目なのは、SunnyPayのようにRI購入時にも5%の割引が適用されるサービスの存在。割引率だけでなく、AWS本来の構成や割引ロジックを維持しながら、請求業務も効率化できる――そんな方法について以下の記事でご紹介します。