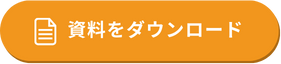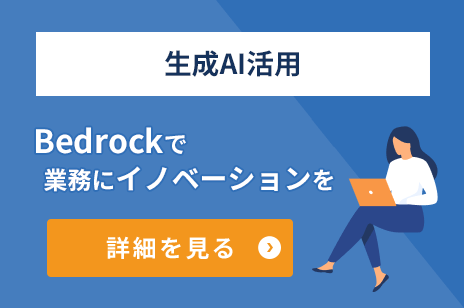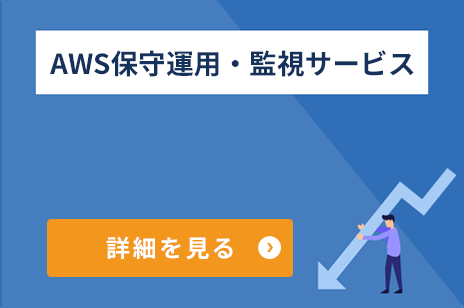AWSを本格的に使い始めると、どうしても気になってくるのが「クラウド料金の高止まり」です。オンデマンドで使い続けるよりも割引が効く仕組みとして、リザーブドインスタンス(RI)を導入している企業も多いでしょう。
しかし最近では、より柔軟に使える割引制度「Savings Plans(セービングスプラン)」を活用する企業が増えてきています。
とはいえ、RIとの違いがわかりにくいのも事実です。
どのように活用すべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、Savings Plansの基本的な仕組みから、RIとの違い、活用のポイントまでをわかりやすく解説します。
この記事はこんな人にオススメ!
- AWSコストを抑えたいが、RIとSavings Plansの違いがよくわからない
- なんとなくRIを使ってきたけど、最近はSavings Plansが主流と聞いて気になっている
- 社内でどちらを導入するか判断を求められ、迷っている
1.Savings Plans(SP)って何?

AWSの料金体系は複雑です。とくにEC2やFargate、Lambdaのようなサービスは、オンデマンド料金で使い続けるとどうしてもコストが膨らみがちです。
こうした課題に対応するために登場したのが、「Savings Plans(セービングスプラン)」という割引制度です。
Savings Plansは、「一定の使用量(ドル換算)を1年または3年コミットする代わりに、割引を受けられる」という仕組み。たとえば「1時間あたり5ドル分使う」というプランを契約すれば、その5ドル分までは最大66%の割引が適用されます。
ポイントは、割引の対象がインスタンス単位ではなく「時間あたりの利用金額」であること。これにより、より柔軟な割引適用が可能になっています。
2.リザーブドインスタンスとの違いはここにある
Savings Plansの登場以前、AWSの定番割引手段といえば「リザーブドインスタンス(RI)」でした。
RIも1年/3年単位の契約で割引を受けられる点では同じですが、両者には大きな違いがあります。
まず最も大きな違いは、「柔軟性」です。
RIは、購入時にインスタンスタイプ(例:t3.medium)やリージョン、OSなどを細かく指定する必要があり、あとから変更ができません。一方、Savings Plans(特にCompute Savings Plans)は、インスタンスタイプが変わっても割引を受けられるため、使い方の自由度が高くなっています。
また、割引の適用範囲も異なります。RIはEC2とRDS、Redshift、ElastiCacheに限定されますが、Savings PlansはEC2だけでなく、FargateやLambdaにも適用可能です(Compute SPの場合)。
違いをざっくりまとめると、以下のようになります:
| 比較項目 | リザーブドインスタンス(RI) | Savings Plans(SP) |
| 割引対象 | EC2、RDS など特定サービス | EC2、Fargate、Lambda(Compute SP) |
| 柔軟性 | インスタンスタイプやOS固定 | インスタンスタイプ・OSをまたいで割引可能(Compute SP) |
| 契約単位 | インスタンス単位で購入 | 時間あたりの利用額でコミット |
| 運用のしやすさ | 構成変更に弱い | 柔軟に対応できる |
Savings Plansの方が“使いやすくて適用範囲が広い”という印象を持つ人も多いですが、その分、契約額の算出や適用状況の把握がやや難しくなっています。
3.Compute SPとEC2 SP、どっちを選べばいい?
Savings Plansには大きく分けて2種類あります:
- Compute Savings Plans:最も柔軟性が高い。インスタンスファミリーやOS、リージョンをまたいで割引が適用される。EC2、Fargate、Lambdaに対応。
- EC2 Instance Savings Plans:割引対象はEC2のみ。ただし、インスタンスファミリーとOSは固定される。
使い方によって、どちらが適しているかは異なります。
たとえば、開発環境と本番環境でインスタンス構成が異なる場合や、今後の構成変更が見込まれる場合は、Compute SPが適しています。
一方で、同じインスタンスを長期間・安定的に使い続ける見込みがある場合は、より割引率の高いEC2 SPの方が良い選択肢になることもあります。
いずれにせよ、Savings Plansは事前に“どのくらいの利用が発生するか”を予測する必要があるため、正確なコスト把握と、契約前のシミュレーションが欠かせません。
4.SPは万能じゃない?気をつけたいポイント
Savings Plansは柔軟で便利な反面、いくつかの注意点もあります。
まず大前提として、一度契約したら原則としてキャンセル・変更はできません。
契約期間中は、コミットした金額分を「使っていようが使っていまいが」課金され続けるため、使いきれなかった場合はその分が損失になります。
さらに、Savings Plansの割引は「適用されたかどうかが分かりにくい」という声もよく聞きます。RIのように“どのインスタンスに適用されたか”を明確に把握しづらいため、経理部門との間でコスト効果の認識にズレが生じやすくなるのです。
また、契約時には以下の3種類の支払い方法が選べます:
- 全額前払い(最も割引率が高い)
- 一部前払い
- 前払いなし(月額払い)
割引率だけを見て前払いを選ぶと、キャッシュフローを圧迫するリスクもあります。費用対効果だけでなく、自社の財務状況も考慮して選ぶ必要がある点も忘れてはいけません。
まとめ:「柔軟性」と「確実性」、どちらを取るかが選択の鍵
いかがでしたか?
リザーブドインスタンスとSavings Plansは、どちらもAWSのコスト削減には効果的な手段です。
しかしそれぞれに向き・不向きがあり、一概に「どっちが良い」とは言えません。
- 柔軟に構成を変えていきたい企業や、複数サービスを横断的に利用している企業 → Savings Plans(特にCompute SP)
- 安定した構成で長期間同じインスタンスを使い続ける → RI or EC2 SP
最も大切なのは、自社の利用傾向を正確に把握した上で判断することです。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました!
AWSコスト削減セミナー、参加受付中!

「気づかぬムダをどう見つけ、どう減らすか?」
そんな疑問に応える、AWSコスト削減に特化した無料ウェビナーシリーズを開催中です。
次回は、「RI/SPの活用と料金管理の見直し」をテーマに、コスト最適化に直結する4つの代表的な施策を解説します。
“契約”と“構成”の両面からAWSコストを最適化するポイントを30分で凝縮してお届けします。
Savings Plansを“ちゃんと活かす”ための資料はこちら
SPの契約設計から割引の適用範囲、経理部門との連携ポイントまで、実務に役立つ内容を一冊にまとめました。
SunnyPayなら、Savings Plans契約時にも5%割引が適用されます。
柔軟性とコスト最適化を両立したい方は、ぜひご覧ください。
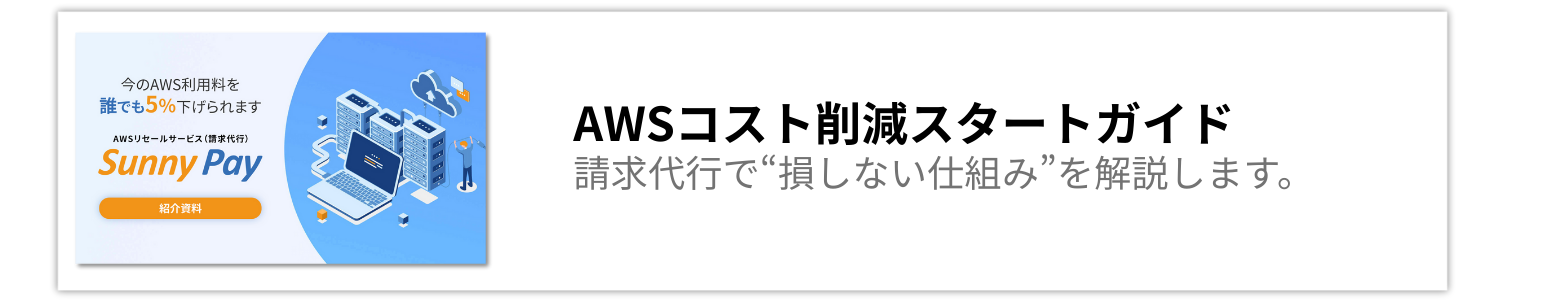
次回予告:契約してからが本番?Savings Plansの運用・可視化のリアル
後編では、Savings Plansを契約した後に待っている“運用のリアル”について掘り下げていきます。
- 適切なコミット額はどうやって決める?
- 割引の適用状況はどう確認する?
- 経理担当に割引効果をどう説明する?
- SunnyPayならSavings Plansでも5%割引が適用できる?
そんな実務的な疑問に答えながら、導入後の落とし穴も含めて詳しく解説していきます。